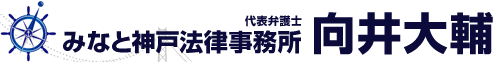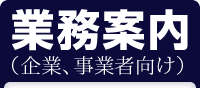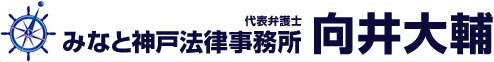公正証書遺言・自筆証書遺言がそれぞれ無効とされた事例(東京高判H27・8・27)
2018/06/06
一 公正証書遺言につき、遺言者が公証人及び証人に対して遺言内容を具体的に語ることをしなかったもので、口授の要件を備えていなかったとして、無効であるとした事例
二 公正証書遺言の前に作成された自筆証書遺言につき、遺言者が遺言の意思を失っていたとして、無効であるとした事例
東京高等裁判所 平成27年8月27日 判決
【判旨】
① 公正証書遺言について、遺言者の意識状態・身体状況、遺言者が公証人及び証人に対して遺言内容を具体的に語ることをしなかったこと等から、遺言者の遺言の趣旨を理解することができるように口授したものとは認められないとして、無効とした。
② ①の公正証書遺言に先立つ自筆証書遺言について、その後に公正証書遺言の作成を試みたこと、自筆証書遺言作成後に、自身で持ち帰ることも、保管を他に託すこともなかったことなどから、遺言意思がなく無効であるとした。
【事案の概要】
・被相続人Aは、公証役場訪問前には高度の意識障害によりコミュニケーションが困難な状態になることがあった。
・Aは、公証役場訪問後には、救急外来を受診し、意識障害を生じ、肝性昏睡と診断された。
・公証役場において、Aは公証人に対し、「(共同相続人(※)である)Y1に全部」「(共同相続人である)Y2にも。」と述べる以外は何も言わず、証人(※)らもこれらの発言以外は見聞きしていなかった。
※共同相続人・・・例えば遺言者に配偶者と子どもがいる場合や、子どもが複数いる場合など、相続人が複数存在する場合の相続人を「共同相続人」といいます。
※証人・・・公正証書遺言を作成するには、証人二人以上の立会いが要件とされています。
・しかし、公証人の作成した遺言案は、Y1に10分の5、Y2及び(共同相続人である)Xらに各10分の1とするものであった。
・公証人が、遺言案を読み上げて内容を確認したところ、Aは頷くのみで何ら具体的発言をすることはなかった。
・Aは、自筆証書遺言の作成を試みて、何枚か作成したものの、いずれもうまくかけず、Y1が四か所に訂正印を押さなければならなかった。
・Aは、作成した自筆証書遺言を持ち帰らず、また、作成に立ち会ったAの兄嫁であるBに保管等を託すこともしなかった。
・Aは、自筆証書遺言について、Bから遺言書として通らないと言われて公正証書遺言を作成することを勧められ、公証役場を訪問して公正証書遺言を作成した。
【判断内容】
①Aの意識障害や肝性昏睡と診断を受けたことについて
⇒Aの意識状態や身体状態に一定の変動があり、具体的な応答をし得る程度の意識状態や身体状況にあったとみるには相当の疑義が存するとしました。
<ポイント>
公正証書遺言の方式として、「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」が必要となります(民法969条2号)。
「口授」を要する趣旨について、控訴審は、遺言者の財産を誰に対してどのように処分するかといった遺言の具体的な内容について、遺言者自らが、自分の言葉で、公証人に対して語ることで、遺言者の真意を確認し、その真意を確保し、その正確を期するための適切な手段として、公証人による「読み聞かせ」(同条3号)及び遺言者による「承認」(同条4号)とは別の方式である「口授」を規定しているものだと判断しています。
この「口授」の程度等を判断するためには、遺言者の意識状態や身体状態について、公証人に対し、具体的な応答が可能であったかを詳細に検討する必要があります。
本件においては、遺言者が、肝性脳症等により入院し、その期間中には、意識障害を伴って、自己判断、読み書き、家族とのコミュニケーションが困難な状態となることがあったほか、公証役場訪問の当日の夕方には、二日前から呂律が回りづらいところがあるとして病院を受診するなど、遺言者の意識状態や身体状況が非常に不安定であったことから、具体的な応答ができたとは考えにくいと判断されました。
②Aが遺言内容を具体的に語らなかったが、公証人の作成した遺言案には具体的な相続割合が書かれていたことについて
⇒Aが自ら発した言葉自体により、これを聞いた公証人のみならず、立ち会っている証人もが、いずれもその言葉で遺言者の遺言の趣旨を理解することが出来るように口授したものとは認められないとしました。
<ポイント>
一般的に、公証役場において公証人が作成した遺言書には、高度の信用性があります。
しかし、その具体的な内容が遺言者の真意を確保したものであるか否か、すなわち遺言者の「口授」に基づいて作成されたのか否かが慎重に判断されているのが特徴的です。
控訴審は、「口授」を、公正証書遺言の根幹をなす方式と位置づけ、「口授」と言えるためには、「用語、言葉違いは別として、遺言者が自ら発した言葉自体により、これを聞いた公証人のみならず、立ち会っている証人もが、いずれもその言葉で遺言者の遺言の趣旨を理解することが出来るものであることを要する」としています。
本件においては、遺言者の意識状態や身体状況に一定の変動があったこと、「Y1に全部」「Y2にも」との発言以外には具体的な発言を何らしなかったことなどから、「口授」したものとは認められないとされました。
③公証人が内容確認のため遺言案を読み上げても、Aが頷くのみで具体的発言をしなかったことについて
⇒公証人の質問に対する肯定的な言辞、挙動をしても、これをもって、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したということはできないとしました。
<ポイント>
「口授」と認められるために、どの程度の具体的発言が必要となるかについての参考として、従前の判例においても、首を振る程度の返事をした場合や、肯定または否定の挙動をしたに過ぎない場合に口授があったとはいえないとされています(大判大7.3.9、最二判昭51.1.16)。
「口授」と認められるためには、受動的に頷くだけでは足りず、あくまでも能動的に、遺言者自らが、自らの言葉で語ることが必要となり、その内容としても、言葉自体により、公証人や証人が、遺言者の遺言の趣旨を理解することが出来るものであることを要します。
④自筆証書遺言のために複数書き直しがされ、作成後も、Aが持ち帰りもせず、保管等を託すこともせず、その後、勧めを受けて公正証書遺言を作成していることについて
⇒遅くとも公正証書遺言の作成を勧められた時点までに、自筆証書をもって遺言書とする意思自体を失っていたとして、自筆証書遺言は遺言意思がなく無効であるとしました。
<ポイント>
A本人が、遺言書の作成を試みて、表題、本文、日付及び氏名を書いた遺言書が形式的には存在しているものの、同遺言書の作成経緯のみならず、作成後の事情等をも考慮して、Aが同遺言書を自筆証書遺言とする意思はなかったものと判断されました。
【コメント】
近年、「終活」という言葉がよく聞かれるようになりました。
決してネガティブな言葉ではなく、むしろ、これまでの人生を振り返りながら、今後の人生を考え、そして自身の亡き後も、葬儀や相続等の場面で自らの意思を実現し、さらに大切な方々が困ることのないように準備をする、前向きな活動ととらえる方が増えているようです。遺言書を作成することは、最も重要な終活の一つと言えるのではないでしょうか。
ご自身の亡き後、ご自身の最終の意思を生かすことが出来るように、また、大切なご家族等が相続で争うことのないように、問題が生じない有効な遺言書を準備したいところです。
そのような観点から、今回の判例を踏まえて、遺言書を作成するにあたってのポイントをまとめました。
(1)心身ともに健康なうちに
遺言書の作成というと、高齢になってからと考える方が多いかと思います。
しかしながら、本件のように、介護を要する状態になってからでは、遺言書作成に困難を伴うことが多く、さらに、公正証書遺言作成時の「口授」との関係でも、判断能力やコミュニケーション能力に問題を生じかねません。さらに言えば、重度の認知症等を患っていた場合、遺言能力(自分の遺言の内容及びその結果生じる法律効果を理解・判断できる能力)の有無が問題となり、遺言の有効性について争いが生じることも考えられます。
このことからすると、心身ともに健康なうちに、遺言書の作成を始めることが一つのポイントになると言えます。
財産の状況も、人間関係も、生きている限り変化していくものですが、遺言は何度でも内容を変更し、作成し直すことが出来ますので、早めに作成しておいてもデメリットは特にないと言えるでしょう。法律上は、満15歳になれば、未成年者であっても、単独で遺言ができる(民法961条)ものとされています。
一方、現在すでに、重度の認知症や精神病を患い、成年被後見人となられている方も、事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2人の立会いを要件として、遺言をすることが出来ます(民法973条)。また、被保佐人、被補助人となられている方については、遺言能力には制限はありません。
(2)自筆証書遺言(民法968条)は必ず専門家のアドバイスを
自分だけで作成する自筆証書遺言は、作成が簡便で、費用もかからず、遺言書作成の事実や内容を秘密にしておくこともできます。
しかしその一方で反面、偽造や変造の危険、紛失の恐れは高いと言えます。
また、法で定められた方式に従って、自分自身で作成しなければならず、方式の不備や内容が不明確などの理由でしばしば有効性や文面の解釈が争われるのも、この自筆証書遺言です。
作成のポイントとして重要なのは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を「自書」し、これに押印するという方式に不備の無いようにすることです。「自書」することで、その筆跡から、本人が書いたものであることを確認でき、遺言書が本人の真意に出たものであることが保障されると考えられています。したがって、パソコン等では作成できません。
日付は、その当時の遺言者の遺言能力の有無を判断したり、2通以上の遺言書がある場合にその前後関係を判定したりするための重要な記載事項です。そのため、「〇年〇月吉日」などの曖昧な記載ではなく、年月日を特定して正確に記載しなければ遺言書自体が無効とされる場合がありますので、注意が必要です。
遺言書の作成自体を秘密にしておきたいということでなければ、信頼できる方に遺言書の保管場所を伝えておくと、亡くなった後の遺言書の発見、検認手続き等がスムーズにできることとなります。
(3)できる限り公正証書遺言(民法969条)で作成を
当事務所でご依頼を受けて遺言書を作成する場合、基本的にはこの公正証書遺言の方式をおススメしています。
法律事務所によって進め方は様々だと思いますが、当事務所で受任した場合には、財産の状況や、相続関係を確認することや、誰に対してどのように財産を残したいのかということは当然として、特にお断りされない限りは、そこにはどのような背景があり、どのような想いがあるのか、ということを詳細にお聞きしています。
作成者の方がこの遺言を作成しようと思うにいたった背景は遺言書の根幹であると考えています。
これらをお聴きすることで、よりご本人の意思を反映できる内容をご提案させていただいております。
これは遺言全般に言えることですが、遺産のことのみならず、例えば、葬儀や納骨についての希望を記載することもできますし、なぜそうした記載にしたのかの理由を書くこともできます。
このようにして作成した遺言書案を基に公証人に遺言書を作成してもらい、公証役場において証人2人以上(当事務所の弁護士2人が証人になることが可能です)とともに、遺言書に署名・押印することとなります。
ご自身で、この方式の遺言を作成される場合のポイントとしては、本件において問題となった「口授」を正確に行うためにも、公証役場に行かれる前に、ご自身の意向をできる限り具体的にメモにして、それを持参することが重要となります。そうすることで、より正確にご自身の意向を反映した遺言書を作成できるでしょう。
(4)障害のある方が作成するための方法
公正証書遺言を作成する場合、遺言者が遺言の内容を公証人に「口授」したり、公証人が筆記した内容を遺言者に「読み聞かせ」たりする手続きを踏みます。
ですが、例えば遺言者が障害により言葉を話すことが出来ない場合は、「口授」を通訳人の通訳による申述または自書に換えることができ、遺言者が聴覚障害をお持ちの場合は、「読み聞かせ」の代わりに通訳人の通訳により伝えることが出来るとされています。
具体的なことは当事務所までお問い合わせいただければ、ご希望の場所へ出向いてご説明いたします。
(5)内容を秘密にしておきたい場合(秘密証書遺言・民法970条)
遺言書を作成したこと自体は公にしてもいいけれど、その内容は秘密にしておきたいという場合は、秘密証書遺言という方式があります。
これは、公証役場において、その証書が本当に遺言者の作成した遺言書であるということのみを証明してもらう方式で、遺言書の内容自体は、ご自身で作成することとなります。この場合、署名は自書する必要がありますが、自筆証書遺言と異なり、遺言書の本文、日付、住所は、自書しなくてもよく、パソコン等でも作成できるというメリットがあります。
遺言者の遺言書であることは公証人及び証人により証明されているので、筆跡により確認する必要がないということです。
(6)何度でも作成できます。
遺言は、生きている間は、何度でも変更することが出来ます。
複数作成した場合、その一番新しいものが、遺言者の意思として扱われることとなっています。
本稿では、遺言について、基本的な方式をポイントとともにご紹介してきました。
遺言書を作成することは、まだまだ先と感じられる方も多いかもしれません。
ですが、遺言書の作成は、それを通じて、現在までの自分の人生とそこに携わってきた方々をゆっくりと想い、振り返る一つのきっかけともなります。
それによって、今日からの人生を一日一日大切に生きたいと感じることができるようになったというお声をいただくこともあります。
遺言書作成に早過ぎるということはないのかもしれません。
遺言書の作成についてお考えの方やご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。
みなと神戸法律事務所
代表弁護士 向井 大輔